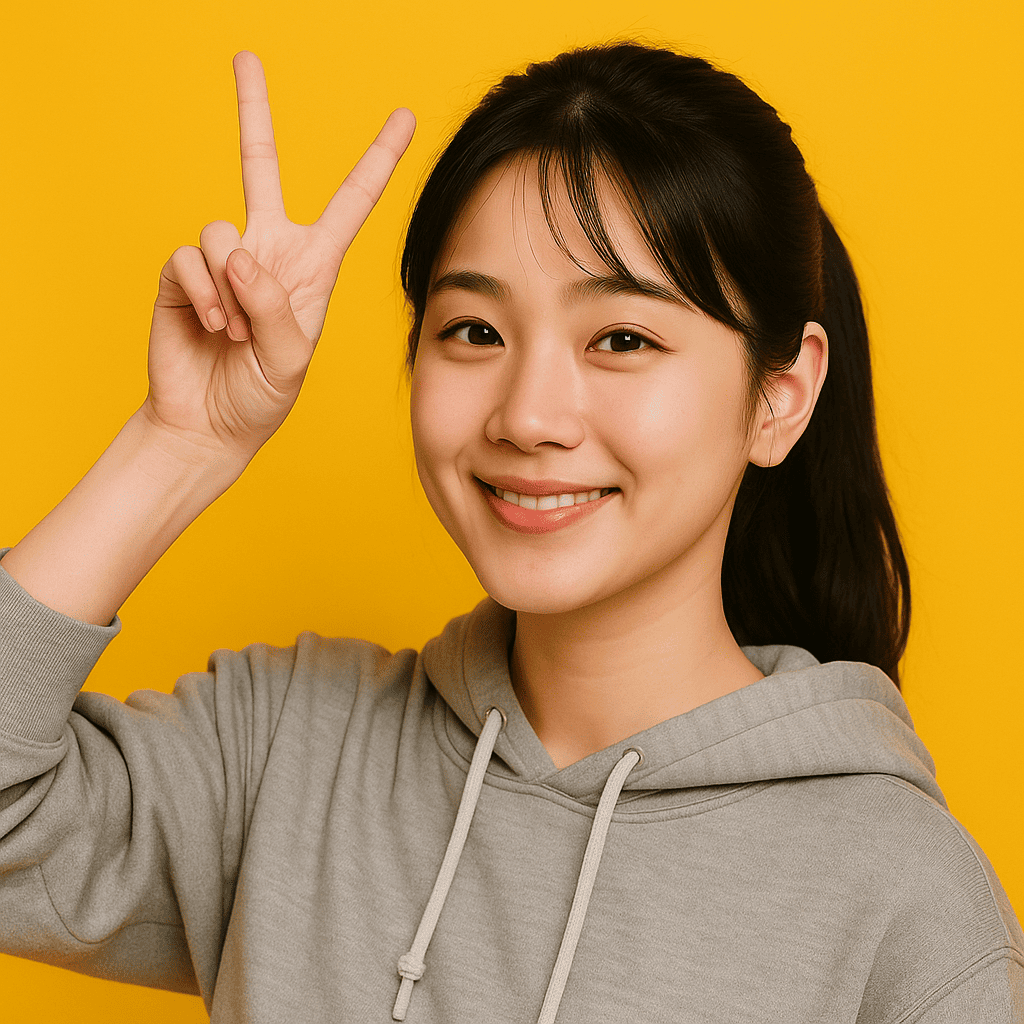5年後にはなくなる!?臨配さんの将来についてAIに予測してもらいました!!
人生で怪我や病気で働けなくなる割合は!? まず当社の応募データから見ると50代以上の求職者からの応募が約7割を占めます。 またCHANGEメンバーの平均年齢は54.6歳と、関東全体で臨配として働いている人の多くは50代以上だと予測できます。 大手損保会社のデータを元に、人生において入院して働けなくなる可能性を、年代別に表にしました。 年齢が上がれば、上がるほど病気や怪我で働けなくなる割合は高くなっているのが顕著にデータとして現れています。 20代と60代ではリスクは3倍以上に上がり、50代以上では約6人に1人が何かしらの病気や事故で働けなくなった経験があるということです。 あと5年が限界!?臨配という職業はなくなる!? 新聞業界の構造自体が限界に近づいている中で、今後臨配需要(臨配依頼)が減るのは確実です。数年後には関東全体でも月に数件程度しかない臨配依頼を100人程度の臨配さんたちで奪い合う状況になります。 10年後には「臨配」なんていう仕事もあったねという話も現実的な予測として考えられます。 All Posts メンバー限定 臨配 臨配メシ 臨配求人 臨配稼働ランキング 臨配需要と臨配依頼件数についてAIに予測してもらいました!! 2025年11月7日/続きをよむ 今後の臨配業界についてAIによる分析とCHANGEと他の臨配団を比較してみました!! 2025年9月20日/続きをよむ 臨配さんの将来についてAIに予測してもらいました!! ■ 予測①:生活保護の受給者が増える 無年金・無保険・貯金なし 家なし 60〜70代で再就職先がないという条件は、生活保護要件に完全に合致します。 新聞業界の衰退地域から、自治体福祉へ流れるパターンが急増すると予測されます。 ただし問題は、 生活保護は「住所」が必要 → 住所がないと申請できない 病気や怪我で動けなくなるまで申請しない人も多い そのため、実際には生活保護にたどり着けず、野宿・ネットカフェ生活・簡易宿泊所生活が増えるというケースが現実的です。 ■ 予測②:新聞販売店に「アルバイト」として再雇用されるが… 元の臨配より収入は大幅に下がる 手取り10〜12万円前後 社会保険に入れてくれない販売店も多い 高齢になると体力的に継続が困難 結果的に臨配需要(臨配依頼)はさらに減少する つまり、アルバイトとして細く長く生存はで